| 弓長嶺鉄鉱万人坑 遼寧省遼陽市. 遼陽市弓長嶺区の幹線道路と鉄道線は、平地が広がる広い谷に沿って延びている。その広い谷の両側に山地が続き、その山々がそれぞれ鉄鉱石の採れる鉱山だ。 弓長嶺万人坑の入口は幹線道路沿いにあり、道路脇の駐車場の目の前に石造りの門柱が立っていて、赤い大きな文字で弓長嶺愛国主義教育基地と書いてある。この門の先に続く山地が弓長嶺三道溝万人坑だ。弓長嶺鉄鉱の強制労働で死亡した中国人労工の多くは、主に周辺の三つの大きな谷に大量に捨てられたので三道溝万人坑と呼ばれるようになった。 弓長嶺鉄鉱万人坑の全体像について、李秉剛氏の「万人坑を知る」(東北大学出版社=瀋陽)で確認しておこう(要旨)。 『一九三三年五月から一九四五年八月までに日本は弓長嶺から鉄鉱石を一〇〇〇万トン収奪し、一万二〇〇〇人以上の労工を死亡させた。遺体は主に三道溝などに捨てられたが、埋める場所が無くなると死体焼却炉を作って焼いた。』 写真撮影(2009年9月27日)と解説 青木 茂 . | |
 弓長嶺三道溝万人坑/展示施設跡 弓長嶺万人坑の入口の門を入るとすぐに、コンクリートで固めた直径三〇メートルくらいの円形の広場があり、その広場を取り囲むように橙色の柱が二〇本ほど立っている。遺骨保存館などと共に造られた展示施設だったが、今はコンクリートの床面と二〇本ほどの柱以外は何もない。展示施設跡の脇には、高さ二メートル・幅四メートルくらいの石碑があり、三道溝遺跡紹介という標題と結構長い解説文が刻まれている。 三道溝万人坑に関わる施設は以前は弓長嶺鉱業会社という企業が所有し管理していたが、会社が倒産したあとは、施設を管理する人もいないまま放置されてきた。現在は遼陽市の管理に移り整備計画を申請中で、許可が下りれば、これから整備されることになる。 |
 「万人坑」保存館/外観 展示施設跡から道沿いに一〇〇メートルほど山の中に入ると、「万人坑」と記された銘板と八角形の建物がある。万人坑の発掘現場の上に建てられた保存展示施設である。 |
 「万人坑」保存館/内部の遺骨発掘現場 保存館内に、直径一〇メートル・深さ二メートルくらいの円形の穴があり、穴の中に遺骨が乱雑に山積みされている。遺骨はグチャグチャに重ねられていて、一体一体区別することはできない。鉄鉱山の強制労働で死亡した労工が深い谷に次々投げ込まれた結果がここにある。 |
 「万人坑」保存館/内部の遺骨発掘現場 それにしても、犠牲者には申し訳ないような状態だ。施設は長い間放置されたままの様子で、幾つかのガラス窓が割れ、割れ落ちたガラスが施設内に散らばったままだ。 |
 「千人溝」保存館/外観 「万人坑」からさらに五〇メートルほど山を登ると、「千人溝」と記された銘板と「万人坑」と同じような八角形の建物があり、さらにそこに長方形状の建物が連なって建っている。これも、万人坑の発掘現場の上に建てられた保存展示施設である。 |
 「千人溝」保存館/内部の遺骨発掘現場 八角系の保存館に連なる長方形状の建物は小さな谷に沿って建てられていて、これら建物の内部に遺骨がグチャグチャに山積みされている。亡くなった人を埋葬するというような発想はまるでなく、ゴミでも捨てるように深い谷にどんどん遺体を放り込み続けた結果なのだろう。 |
 「千人溝」保存館/内部の遺骨発掘現場詳細 |
 「万人坑」と展示施設跡の中間の位置の道路から少し山の中に入ったところに遺体焼却炉がある。赤煉瓦を積んで造られたかなり大きなもので、「窓」が三つある焼却炉本体の上に高さ五メートルくらいの赤煉瓦製の四角柱状の煙突が立っている。遺体を捨てる場所がいよいよ無くなり、遺体を焼却処理するために一九四五年に作られた施設だ。 |
 日本軍の監視下で道路建設を行なう弓長嶺鉄鉱の労工 【李秉剛教授(北京)提供写真】.
|  弓長嶺鉄鉱矯正補導院の生存労工・劉再坤さん 【李秉剛教授(北京)提供写真】.
|
 【李秉剛教授(北京)提供写真】.
|
「万人坑を知る旅」index
注意:無断引用・転載はお断りします。引用・転載などを希望される方は、下のメールフォームをとおして、当ホームページの担当者に相談してください。 |
行事案内やニュースなどを不定期に追加・更新します。 時々覗いてみてください。 |
|
「中国人強制連行・強制労働と万人坑」の学習会をしませんか! 中国に現存する万人坑(人捨て場)と、万人坑から見えてくる中国人強制連行・強制労働について考えてみませんか! 「中国人強制連行・強制労働と万人坑」について事実を確認してみたい、学習会や集会をやってみたいと思われる方は、当ホームページ担当者に気軽に連絡・相談してください。日程や条件が折り合えばどこへでも出向き、話題と資料を提供し、できる限りの解説をします。仲間内の少人数の勉強会とか雑談会のような場でもよいですし、不特定の一般の方も参加していただく集会のような形式でもよいです。開催形式・要領は依頼者にお任せします。まずは当方に連絡していただき、進め方などを相談しましょう。 それで、謝礼などは一切不要ですが、資料の印刷と担当者の会場までの交通費実費だけは、依頼される方で負担してくださいね。 当方への連絡は、メールフォームまたは下記メール宛でお願いします。 ⇒ メールアドレス: 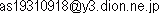 |
青木 茂 著書の紹介
【メールフォームのページへ】 |