| 旅順万忠墓 遼寧省大連市旅順口区. 日清戦争の開戦から4カ月後の1894年11月に旅順(現在の中国遼寧省大連市にある港町)を占領した日本軍が、占領日を含む数日の間に清国軍捕虜と旅順の一般住民を大量殺害した事件を旅順大虐殺という。犠牲者は2万人以上にもなり、犠牲者の遺体を最も多く焼き、その骨灰が埋葬された白玉山東麓に万忠墓が設営されている。 日清戦争 伝統的な宗主国として清(中国)が強い影響力を持つ朝鮮を支配下に取り込むため日本が引き起こした侵略戦争を日清戦争(中国での呼称は甲午戦争)という。 1894年7月25日に黄海上の豊島沖で清の北洋艦隊を日本海軍が攻撃し、続けて、朝鮮に駐屯している清国軍に日本陸軍が奇襲攻撃して戦闘が始まり、8月1日に日本と清が共に宣戦布告し日清戦争(甲午戦争)が「正式」に開戦した。日本軍は、朝鮮国内の戦闘で清国軍を圧倒し、9月の黄海海戦にも勝利し、10月には、朝鮮と清の国境である鴨緑江を越えて清国内に進軍する。そして、11月21日に、遼東半島の先端に位置し北洋艦隊の基地となっている戦略上の重要拠点である旅順を日本軍が占領する。 旅順大虐殺 11月21日に旅順を占領した日本軍は、占領当日の11月21日と、清国軍の組織的抵抗が既になくなっている翌22日以降の3日間ないし4日間に、旅順市内と近郊で、清国軍捕虜と旅順の一般住民を手当たり次第に虐殺した。犠牲者は、武器を放棄した清国軍兵士(捕虜)が2500人、旅順の一般住民が1万8000人にもなり、合計すると犠牲者は2万人を超える。 占領と大虐殺による騒動と混乱が鎮静化した後の11月下旬から、旅順市街と近郊に放置されている犠牲者の遺体の処理を日本軍は始める。そして、気候が暖かくなり遺体が腐乱する前の1895年初頭に、白玉山の東麓、順山街の溝里、黄金山の東麓の主に三カ所に大量の遺体を集めて焼却し、それぞれの「墓」に骨灰を埋葬した。そこには、「清国将士陣亡之墓(清国将士戦死者の墓)」と記す木製の碑が立てられ、女性や子どもを含む一般民衆の虐殺は隠ぺいされた。 万忠墓 日本が犠牲者の遺体を処理した主要な3カ所のうち、焼却された遺体が一番多いのは白玉山の東麓で、1896年に中国(清国)は白玉山東麓に墓碑と廟を建造し万忠墓と命名した。それ以降、万忠墓は3回の修築を経たあと、旅順大虐殺から100年後の1994年に万忠墓の4回目の修築が行なわれる。同時に、万忠墓記念館も新たに竣工し、11月21日に甲午(日清)戦争旅順殉難同胞百年忌が挙行された。その後、2006年に万忠墓は全国重点文物保護単位に登録される。 現地訪問:2017年8月31日 . |
|
 旅順万忠墓記念館正面入口 記念館の中に、かなり広い展示室(資料室)が開設されている。 |
 記念館内の展示室 日清戦争当時の写真や遺品などが配置される展示室が幾部屋もある。 |
 万忠墓享殿‐1 1896年に建立された万忠墓享殿(記念館展示室内にある展示写真)。 |  万忠墓享殿‐2 現在の万忠墓享殿。万忠墓の正面入口になるが、普段は通り抜けることはできない。 |
 万忠墓‐1 正面入口(万忠墓享殿)を通り抜けたところから見る万忠墓の全体像。 |  万忠墓‐2 1994年に改修された万忠墓。白い記念碑も新たに造られたものだ。 |
 万忠墓‐3 |  万忠墓‐4 |
 「万忠墓」碑と万忠墓享殿 正面入口(万忠墓享殿)から入ると、右手に「万忠墓」碑が設置されている。 |  「万忠墓」碑 1896年に建立された「万忠墓」碑がこの位置に移設されている。 |
 犠牲者追悼式 犠牲者追悼式を勤める参列者の背後に「万忠墓碑」碑が見える。 |  1922年に建立された「万忠墓碑」碑がここに移設されている。 |
 李秉剛氏提供写真 |  旅順大虐殺の写真‐1 李秉剛氏提供写真 |
 旅順大虐殺の写真‐2 李秉剛氏提供写真 |  旅順大虐殺の写真‐3 李秉剛氏提供写真 |
「万人坑を知る旅」index
注意:無断引用・転載はお断りします。引用・転載などを希望される方は、下のメールフォームをとおして、当ホームページの担当者に相談してください。 |
行事案内やニュースなどを不定期に追加・更新します。 時々覗いてみてください。 |
|
「中国人強制連行・強制労働と万人坑」の学習会をしませんか! 中国に現存する万人坑(人捨て場)と、万人坑から見えてくる中国人強制連行・強制労働について考えてみませんか! 「中国人強制連行・強制労働と万人坑」について事実を確認してみたい、学習会や集会をやってみたいと思われる方は、当ホームページ担当者に気軽に連絡・相談してください。日程や条件が折り合えばどこへでも出向き、話題と資料を提供し、できる限りの解説をします。仲間内の少人数の勉強会とか雑談会のような場でもよいですし、不特定の一般の方も参加していただく集会のような形式でもよいです。開催形式・要領は依頼者にお任せします。まずは当方に連絡していただき、進め方などを相談しましょう。 それで、謝礼などは一切不要ですが、資料の印刷と担当者の会場までの交通費実費だけは、依頼される方で負担してくださいね。 当方への連絡は、メールフォームまたは下記メール宛でお願いします。 ⇒ メールアドレス: 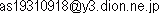 |
青木 茂 著書の紹介
【メールフォームのページへ】 |